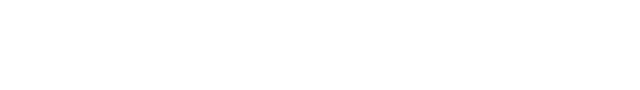適応障害への対応
今日は、精神科産業医の立場から、「適応障害」のさまざまな問題点を考えてみます。
基本的に「適応障害(職場不適応あるいは適応不全)」では、ストレス要因や緩衝因子をコントロールしてストレス反応を低減させていくことが治療になります。
そのため、抗うつ薬を服用し安静を保つ必要があるうつ病など内因性疾患とは治療方針が全く異なります。
『人間関係の問題やハラスメントと適応障害』の冒頭で挙げた、《「適応障害のため3ヶ月の休職を要する」という診断書を職場に提出した社員さん》の場合を考えてみましょう。
人間関係の問題やハラスメントと適応障害
社会保険労務士さんは、「事情をヒアリングしたのちに会社判断で休職を認めるかどうか決めるべき」との意見を出されていましたよね。
会社には従業員に対して《安全配慮義務》《合理的配慮義務》がありますから、「主治医の意見に従うこと」が正解となります。
休職にまつわる問題点
しかし休職という状態は、労働者が《自己保健義務》を全うできずに労働力を提供できない状態なので、労働契約の不履行(債務不履行)として解雇に相当します。しかし、私傷病を理由に温情措置で解雇を猶予してもらっている状態です。
労働力を提供できませんから、当然のことながら賃金は発生しません。それまでに積み立てた保険料から傷病手当が支払われますが、社会保険料は毎月支払わなければならないため、手取額は勤務していたときの半分ほどになってしまします。
また休職した労働者は、もともとの労働契約をまっとうするために、なるべく早く職場に復帰するよう努力する義務が生じます。
内因性のうつ病では休職し自宅療養が必要ですが、「適応障害」の場合はうつ病と同じような対応をすると休職が長引き、挙げ句の果てに退職してしまうこと人が8割以上いると言われています。
「適応障害(職場不適応あるいは適応不全)」の人は、休職することでストレス要因から離れることができますが、「疾病性」に伴う症状が問題なのではなく「仕事ができない」という「事例性」が問題ですよね。
そのため、休職は根本的な解決にならず、問題の解消を先延ばしにしているに過ぎない、と考えられるわけです。
『適応障害の診断に潜む発達障害特性』で述べた、「発達障害素因(自閉スペクトラム症(ASD))あるいは発達特性(非障害性の発達障害特性(AS特性))を基盤にもつ適応障害(不適応)」の人は、生活リズムの乱れを起こしやすく、とくに昼夜逆転に近い睡眠覚醒リズムの乱れが生じてしまうと、新陳代謝や意欲の低下を引き起こし、不適応がますます助長されてしまい、復職に対するハードルが高くなってしまう、というデメリットがあります。
適応障害の診断に潜む発達障害特性
ここまで考えると、果たして本当に「休職が必要だったのか?」、と改めて問わざるを得なくなります。
いろんな社員さんと面談していると、うつ病や双極性障害の診断で、さまざまな薬がてんこ盛りにされていて、これでは薬の影響で仕事どころではないだろう…と感じることがよくあります。
「うつ病をともなう適応障害」のような、診断基準をご存じない精神科医の先生の診断名を見かけることもありますが、発達障害特性がある場合の多くは、適応障害・うつ状態⇒うつ病⇒双極性障害と診断が変わっていくことが多いようです。
「適応障害(職場不適応あるいは適応不全)」の治療の原則は、抗うつ薬や抗不安薬などの薬物療法ではなく(むしろ禁忌)、あるいは、うつ病と同じように休職し安静療養することでもないことは、少し考えるとわかりますよね。
これは、仕事の量・仕事の内容・人間関係・職場環境など「業務関連性」によって引き起こされた「事例性(勤怠・安全・パフォーマンス)」の問題は、薬では解決できない、という当たり前の結果なのです。
しかし、精神科医にこの部分を見極めてもらえなかった社員さん(患者さん)は、ただ薬漬けにされて、休職が長引くだけでなく休職を繰り返してしまい働き続けることが難しくなる、という人生の問題が生じてしまいます。
「適応障害(職場不適応あるいは適応不全)」の治療は、ストレス反応を引き起こしたストレス因(仕事の量・内容、対人関係)を、その人が耐えられる範囲に調節すること(環境調整)に尽きるのです。
休職した労働者の側は、ストレス要因によって顕在化した苦手分野を明確にし、労働力を提供するために働く内容と働き方を、会社と交渉していく必要があるのです。
『適応障害の診断をめぐる問題』の冒頭の社員さんは、自己保健義務としてのセルフケア、そして上司への相談としてのラインケア、あるいは保健師さんや産業医など職場の産業保健スタッフへの相談があれば、環境調整などで休職しなくても済んだ可能性がある、ということなのです。
しかし多くの場合、2〜3日の欠勤の後、上司と相談することもなく、いきなり「休職診断書」が提出されます。
さらに『適応障害の診断に潜む発達障害特性』で述べたように、職場側の対応や労働環境の改変が迫られるわけです。
職場では疾病性にとらわれず事例性に着目することで、早く病気に気づき早く医療機関に繋げ、疾病性に関しては医療機関に任せ、早く休養を取らせて、その間に治療を行い、段階的な復職をするといった方法がとられてきた。
これは(従来型)うつ病を対象とすることが前提として作られたと考えられる。
このシステムは、対応疾病の前提として、発症前の機能が通常レベルで問題なく、疾病により機能低下をきたし、休養や治療(主に薬物療法)で治癒し、機能の回復が得られる、という特徴を持つ疾病であることが必要となっている。
しかし、神経発達症の場合は専門医に繋いだ時点で問題が終結するわけではない。
(中略)
従来の対応を行ったとしても長期に休職したままで職場に戻ってこないか、復職ができても、休職−復職を繰り返してしまうことが多い。
治療によっても問題の本質(特性)は変わらず、事例性は改善されず、職場側の対応や環境の変革という形を迫られる。
出口, 岩﨑. 就労者の精神疾患に神経発達症が及ぼすインパクト─主治医および精神科を専門とする産業医の立場から─. 精神科治療学 37(1): 29-34. 2022
会社はどこまで配慮できるか
会社が《解雇回避努力義務》を講じて、「発達特性を基盤とした適応障害(職場不適応)」の従業員の就労継続をサポートしようとする場合、多部署と交渉して異動先の部署が決めなければならない、従業員の特性に合った業務に従事してもらうために、業務全体を棚卸しして仕事を捻出しなければならない、など、会社のそれまでのやり方の変革を余儀なくされます。
元々過重労働である企業が多い中で、当事者がしなくなった仕事、できない仕事は必ず誰かが代わりに行っている。
それによって産み出される周囲からの感情面への影響は常に考慮しておく必要がある。
周囲への感情的な問題への解決はかなり困難であるが、全体への神経発達症への教育、啓蒙が解決の一助になると考える。
誰しもに濃淡はあるが神経発達症の特性があり、それにより配慮を許容してもらおうとする考えがあるが、一般就労者が理解することは案外難しい。
出口, 岩﨑. 就労者の精神疾患に神経発達症が及ぼすインパクト─主治医および精神科を専門とする産業医の立場から─. 精神科治療学 37(1): 29-34. 2022
このように、他の従業員に波及する影響も考える必要が出てくるため、当該社員との契約を「障害者雇用」に変更するという方法もあります。
障害者雇用への切り替えは、当該社員が社内の業務をある程度知っているため、新規で障害者雇用を行うよりリスクも少なく、周囲からの配慮も得られやすいというメリットもあります。
精神障害者保健福祉手帳を取得するためには、半年以上の継続治療が必要であり、この間、会社の体制整備のための時間として休職を使う方法もあります。
最終的には本人が障害者雇用への契約変更に同意するかどうか、が問題ですが、就労継続を考えた場合、考慮するだけの価値はある、と考えられますよね。
院長