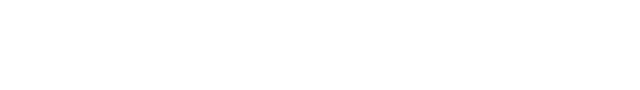手を放す
 その日最初の患者さんを前にした瞬間、私は覚悟を決めました。自分から手を放すということです。
その日最初の患者さんを前にした瞬間、私は覚悟を決めました。自分から手を放すということです。
それはまさに両手を広げて水の中にダイブするような感覚でした。「わからないので教えてください」という気持ちで患者さんに訊き、患者さんの声を聴きました。
するとどうでしょう。あんなに口数が少ないと思っていた患者さんが、一生懸命に自分の言葉で自分のことを私に教えてくれるのです。そして、話しているうちに患者さんの目に力が宿り輝きが増し、表情が生き生きとしてきたのです。
問題が解決したわけではないのに、なぜか退室するその背中には自信すら漂っているように私には感じました。私は目の前で何が起こったのかすぐには理解できませんでした。
次の患者さんにも、その次の患者さんにも、私は自ら手を放すことから始めました。すると、患者さんのほうから私の手を取り、下へ下へと私を連れて行ってくれるのです。そして患者さんのタイミングでまた一緒に浮上してくるのです。私は、診察室にいながら患者さんと二人で海の中を泳いでいるような気がしました。
あぁ、先生が私に伝えたかったのはこういうことだったのか。生野先生が前日の夜、私に繰り返し言っていた言葉。
「自分から手を放しなさい。そして患者さんに訊きなさい。患者さんに教えてもらいなさい。」
私は初めてその意味を体感した気がしました。ジェニーさんは著書の中でこんな風に語っていらっしゃいますよね。
「皮肉にも、回復への道を全身全霊で進むためには、何かを完全に手放す必要がありました。体型や洋服のサイズやそのほか周りの何もかもをコントロールし続けながら、同時に上手に回復していこうとするのは無理だということに気づかされました。
(中略)
「手放す」というのは、さらりと印刷されているといかにも簡単そうに見えますが、私にとっては本当に大変な作業でした。手放して進むためには、私を助けようとしてくれている人たちを、今まで以上に心から信じきらなければいけませんでした。」
ジェニー・シェーファー、トム・ルートレッジ著 「私はこうして摂食障害(拒食・過食)から回復した」より
私にとってもやはり、「手放す」ということは簡単なことではありませんでした。
私は今まで、患者さんのことも自分自身のことも信じきれていなかったのだろうと思います。本当の意味で患者さんを信じていなかったから、「私が何とかしなければ」と思い込んでいましたし、私が私を信じられなかったから、私は「ちゃんとした治療者」になろうと必死になっていたのです。
けれどもそれは完全に間違いでした。私に必要だったのは、「ちゃんとした治療者」というような自分以外の何者かになることではなく、「ありのままの私」「この私でいる」ことだったのです。そのことを先生は私に伝えたかったのだと思います。
それが分かった時、やっと憑き物がとれた感じがしました。前回書いたように「できないの呪い」に取り憑かれていた私には、あれほどの衝撃がなければきっと気づけなかったでしょう。そしてその時の私が壊れるほどの衝撃があったからこそ、初めて患者さんの手を放すことができたのではないかと今は思っています。
振り返ると、患者さんの手を無理やりつかんで離さない私のやり方は、私自身も苦しかったけれど、それ以上にどれほど患者さんを苦しめていたのかと深く反省しています。
自分から手を放すことを体験した後、患者さんたちは途端に自由に泳ぎだしました。そして私も自由になれたのです。この解放感を味わいながら、私はジェニーさんの空中ブランコの話を思い出していました。
空中ブランコのクラスでは、梯子を登り切ったてっぺんで、まず、先生が私のベルトをしっかりとつかんで落ちないようにしてくれました。次に、地面からはるか高い位置の目の前にある空中ブランコのバーを、身体を完全に前に倒してつかむようにと指示されました。このとき先生は、何も考えずに、手放してみてと言いました。考えないようにと言われると考えてしまうものです。でも、そのときに、回復の中で学んできた「手放す」ということを思い出したのです。
(中略)
「跳んで!」と先生が叫び、私は道の領域に一歩を踏み出しました。先生がベルトを放しました。
(中略)
何が待ち受けているかも知らずに、私はともかく信じて、跳んでみることにしました。自分でも驚きましたが、たった1時間のレッスンが終わるときには、私は後ろ向きの宙返りをしてから反対側で待っている空中ブランコ乗りに身体を受け止めてもらうことさえできるようになっていました。
ジェニー・シェーファー、トム・ルートレッジ著 「私はこうして摂食障害(拒食・過食)から回復した」より
私が診察室の中で体験したことはまさに、ジェニーさんの空中ブランコと同じようなものだったのだと思います。
私はこの経験から改めて多くのことに気づかされました。
治療者といえどもやはり「完璧な人間」だとか「ちゃんとした治療者」になる必要などどこにもなかったのだということ。私が私でいることが何よりも大切であること。そして、日々自分と向き合いながら患者さんに教えられ、患者さんから学び、共に成長していく。そんな私でいたいと思っています。