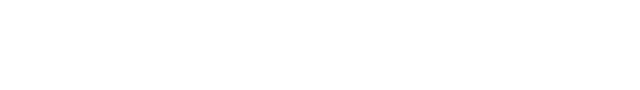双極性障害の過小診断
前回『双極性障害の診断はなぜ難しいのか』で触れたように
双極性障害の7割近くの患者が誤診(過小診断)された経験を持ち、誤診の回数は1回にとどまらず、患者の約4分の1が4回以上の誤診を受けていた。
正しく診断されるまでに受診した医師の数は平均4人であった。
という論文もあります。
(軽)躁状態を呈するまでは双極性障害を疑うことはできても診断はできませんから、誤診という言い方は過激すぎるとしても、治療方針を考える場合、双極性障害を疑う場合と、うつ病と診断する場合ではその後の経過も大きく異なってきます。
たとえば、うつ病相で初発した双極性障害に対して抗うつ薬単剤治療では、
○うつ状態と躁状態を頻回に繰り返す「急速交代化」
○「病相の不安定化」
○不安や不眠、易刺激性などが生じる「賦活症候群(activation syndrome)」
○うつと躁が入り混じる「混合性うつ病」
を起こす可能性が指摘されています。
このような過小診断を避けるためには“Soft Bipolar Spectrum”(Akiskalら)や“双極スペクトラム障害”(Ghaemiら)に代表される「双極スペクトラム」の概念に基づく双極性(bipolarity)の視点が必要になります。
たとえば、難治性うつ状態に対する薬物療法に関して、双極性(bipolarity)のない3人は3人とも抗うつ薬を増量し、2人が寛解に至ったのに対し、双極性(bipolarity)を持つ21人では、抗うつ薬を増量した5人は誰も寛解に至らず、減量した10人は5人が寛解、中止した6人中4人が寛解した、という報告があります。
つまり、双極性(bipolarity)を持つ双極スペクトラム障害では、抗うつ薬は上記の4つの病像の悪化だけでなく
○「うつ病相の遷延」
をきたす可能性がありそうですよね。
さらに。
不安、焦燥感、パニック発作、不眠といった「賦活症候群(アクティベーション・シンドローム)」の症状を呈した大うつ病性障害は、調査した5人全例が双極スペクトラム障害と判定できた、という報告もあります。
ということは、双極性障害は診断が困難で、うつ病と診断されるケースが過半数以上あるにしろ抗うつ剤の効果が非定型的な場合は減薬・断薬など引く治療など、「双極性(bipolarity)という視点を持つこと」が、過小診断による弊害を最小限度にする方策ということになりそうですよね。
ちなみに最近の論文では、双極性障害のために入院し、退院後に気分障害クリニック専門外来での治療を受けた場合は、一般の標準的な治療を受けた場合と比べて再入院率が低く、治療満足度が高かった、ということが報告されています。
院長