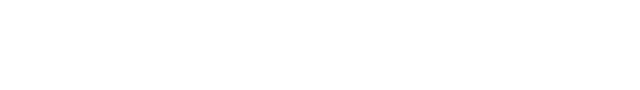摂食障害の鑑別治療学2
対人関係療法は、患者さんへの適合性に応じてエビデンスに基づく精神療法を選ぶという「鑑別治療学」を重視しています。
例えば、神経性大食症(過食症)に対する対人関係療法による治療の初期のマニュアルでは、中心となる対人関係問題領域は「対人関係上の役割をめぐる不和(役割期待の不一致)」か「役割の変化」に関連づけられるとされ、イギリスのレイチェスター摂食障害サービスでの過食症に対する修正対人関係療法「IPT-BN(m)」でもそのようになっています。
一方、水島広子先生の「神経性大食症(bulimia nervosa)用対人関係療法(IPT)マニュアル」では、発症因子ではなく症状維持因子に注目し、上記2つの問題領域に加え、「対人関係の欠如」を限定的に適応し、他者の評価が気になり表面的な対人関係しかもてないという「対人関係の欠如(対人過敏性)」が第二の問題領域の候補になることが多いとされています。
(『摂食障害の準備・誘発・維持因子1』『摂食障害の準備・誘発・維持因子2』参照)
本来の「社会性が乏しく、対人関係の構築や継続が困難」という「対人関係の欠如」はアスペルガー症候群や発達障害など自閉症スペクトラム障害との関連が考えられ、現在のライフ・イベントと気持ちの関係に焦点を当てて治療を進める対人関係療法には不向きとされ、他の3つの問題領域が該当しない場合のみに用いるのみで積極的には選ばれません。
アメリカ国立精神衛生研究所(NIMH)の「うつ病治療における比較研究プログラム(TDCRP)」でも、対人関係療法の「対人関係の欠如」という問題領域しか選べないことは予後不良な因子とされています。
また、睡眠時脳波異常(熟眠感の欠如、多夢、明晰夢傾向)も、対人関係療法に対する反応が有意に悪かったという結果が出ています。
対人関係療法は器質的疾患には不向きということですよね。
またバーバー(Barber)とムエンツ(Muenz)らが報告しているハミルトンうつ病評価尺度(HAM-D)でみると、対人関係療法は未婚、別居、あるいは離婚した患者において有効で、認知行動療法は既婚、あるいは同居者のいる患者に有効だったという結果について、「対人関係上の役割をめぐる不和」に直面している患者に対して、「対人関係上の役割をめぐる不和」という問題領域への焦点づけは対人関係療法において効果が低い領域だということなのだろうか?という疑問が提示されています。
この「対人関係上の役割をめぐる不和」とは、患者と少なくとも一人の重要な他者が、自分たちの関係に対して抱いている期待にズレがある状況で、神経性大食症(過食症)ではとても多くみられる問題領域でもあるのです。
「対人関係上の役割をめぐる不和」の治療目標は、その段階(再交渉、行き詰まり、離別)を見極め、「再交渉」の段階であれば、満足できる結果が得られるよう患者が自分自身の期待や、相手の期待を理解出来るよう援助し、期待を修正したり、問題のあるコミュニケーションを修正し、選択肢を探り、行動計画を選ぶということになります。
「行き詰まり」であれば、「再交渉」の段階に移行させ、「離別」であれば、「悲哀」と同様の作業を行うということになっています。
ここで、「自分自身や相手の期待を理解する」とか、「期待を修正する」「行動計画を選ぶ」ところで、「治療者は特定の方向に患者を導かない」という大前提があります。
これが対人関係療法の限界にも関する部分で、仮に患者の現実認識が誤っていても修正しないということですから、例えば、アスペルガーや発達障害などが背景にあって思い込みによる決めつけタイプの他罰的な人であっても、その認識を尊重し、その中での期待の整理を行うため当然のことながら不和は長引きます。
さらに対人関係療法では、治療者は患者さんの代弁者として機能するため、患者(+治療者の連合軍) vs. 家族という対立関係が成立してしまうことも時にみられます。
対人関係療法は「うつ病の患者に対して良識ある精神科医が普通に行っている支持的精神療法」の有効な部分をマニュアル化して生まれた治療法だったわけですが、特に力動的精神療法の訓練を受けていない人でも理解しやすいように対人関係の問題領域をタイプ分けし、その上でそれらの問題にどのように取り組んでいったらいいのかということがマニュアルで示されています。
対人関係療法は個人療法で、治療者が患者の代弁者となり、コミュニケーションを修正したり、行動の計画を立てる際、治療者が「これが問題だと感じる」逆転移や「治療者自身の価値観」を投影したりすることを、「力動的精神療法の訓練を受けていない人でも理解しやすいように」あるいは家族内精神力動を扱えない人でも治療が進められるように「治療者は特定の方向に患者を導かない」という文言で親切にもマニュアル化してあるわけです。
精神力動や家族療法を扱える治療者であれば常識である「家族構成員間の人間関係のルールに従う」ということも、マニュアル至上主義になりすぎると硬直してしまい、上記の例えのような「対立」の方向に進んでしまうこともありますし、マニュアルには対人関係療法の向き不向きは記載してありませんから、当然のことながら、治療による弊害も出て来ます。
私たちが臨床の場で向き合うのは、マニュアルに書かれている典型例ではなく、千差万別の背景と独自性を持った患者さんですから、対人関係療法による過食症の治療を行う場合もこのような限界も理解した上で、対人関係療法の技法や信念にこだわって強引に進めるのではなく、たとえば「対人関係上の役割をめぐる不和(役割期待の不一致)」を扱う際も、「思春期版の対人関係療法(IPT-A)」で家族の機能不全を扱う時のように「役割の変化」の中で扱うなどの柔軟的な対応をするように、教育的な指示のほか、ジョイニング・リフレーミングなどの能動的な支持、認知の修正や行動の活性化を加味していくなど、患者さんに治療に合わせてもらうのではなく
患者さんや状況に合わせた治療法の柔軟性が必要だということですよね。
院長