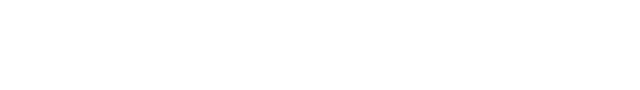食の本質と対人関係療法
ミネソタ大学のノイマーク-スタイナー博士は、週に5回以上、家族と食事をする習慣のある青年期女子は5年後の食行動異常の発症が優位に少なかった、と論文で報告されていました。
面白いことに、家族と食事をする機会が多い女子は、BMIや家族との結びつきの強さとは関係なく、摂食障害(とくに過食や嘔吐)の発症が少なかったのですが、男子では関連性が認められなかったということです。
ノイマーク-スタイナー博士は、女子は食事の準備やその他の家事にかかわることが多く、家庭での食事での個人関係や家族関係に敏感で、影響されやすいからではないか、と考察されていました。
食は栄養摂取と同義ではない。栄養摂取は一人でもできるが、食べることによる紐帯(ちゅうたい:つながりのこと)を一人で作り出すことはできない。
いっけん非合理で、何の必然性もないような食に関わる膨大な知識の数々は、人間が生きるうえで欠くことのできないつながりを作り出しているのである。
このように考えると、ふつうに食べられなくなることの結果を想像するのはたやすい。
その結果とは、食を土台に他者とのつながりを生み出し維持する力の喪失、すなわちその個人の社会的な孤立である。
磯野真穂『なぜふつうに食べられないのか 拒食と過食の文化人類学』春秋社
人とのつながりの中に「食」の本質が存在するということから、スタイナー先生の論文もナルホドと読んだのでした。
これはとりもなおさず摂食障害、とくに過食症に対して対人関係療法による治療が効果を発揮する理由でもあるのです。
対人関係療法というと、対人関係が苦手な性格を克服する、あるいは、問題のある対人関係を修復する、と理解される方もいますが、そうではなくて、重要な他者との対人関係から力をもらい自尊心を高めていくことで、病気を治療する精神療法です。
たとえば水島先生はこう書かれています。
摂食障害の人の中には、「私は対人関係には問題がありません」と言う人もいます。
「協調性」が高めの人も多いので、たしかに一見対人関係のトラブルとは無縁なのでしょう。
トラブルを起こさないように自分を抑えて生きてきた人たちであるとも言えます。
でも、その「トラブルのなさ」の正体を見てみれば、「自分一人ががまんして抱え込む」という対応パターンをとり続けていることがわかり、それによって蓄積されたストレスが病気へとつながっているわけです。
水島広子『拒食症・過食症を対人関係療法で治す』紀伊國屋書店
このような「自分一人ががまんして抱え込む」という「孤立」が、食行動異常の本質、摂食障害の維持因子になることが多いので、対人関係療法ではその部分に焦点をあてていくのです。
しかしふつうに食べられない人々は、やせようと思った過程でこれまで自分が食べ物に与えてきた意味づけを進んで放棄し、そのような人々が作り出した意味づけに従って食べ方や生き方を調節するようになる。
(中略)
食のハビトゥスを捨てるということは、自らの人生の軌跡の中で作り出してきた食べ物や生き方に関わる意味づけを放棄し、他人の作り出した意味に従属して生きることと同じなのである。
(中略)
生きることと、適切な食・正常な心身の間には乖離がある。
生きることの本質は、数値化可能な個体の性質ではなく、人と人のつながりの中にしか現れえないからだ。
適切な食と正常な心身があって初めて人と人とのかかわりが現れるのではない。
まずあるのは人と人とのかかわりであり、適切な食、正常な心身といった概念はその関わりを作り、維持する際に参照されうる一つの知識でしかない。
磯野真穂『なぜふつうに食べられないのか 拒食と過食の文化人類学』春秋社
「自分の気持ちを振り返る」ことで、放棄した意味づけを取り戻し、「他人の作り出した意味」「やせているかどうか」の「評価」に従属する生き方から、「自分はこれでいい」という自己肯定感を高めていくこと、その過程で人と人とのかかわり(つながり)を回復していくこと、つまり対人関係療法では重要な他者との関係を再構築していくことで、上記の摂食障害の発症から維持にいたるプロセスを逆にたどる治療と言えるのかもしれませんね。
院長