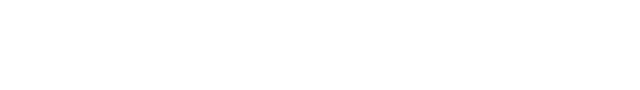摂食障害と依存
『対人関係療法による摂食障害の治療6~過食症の周辺(依存性)』でも触れているように、摂食障害と依存はかなり近い病像を呈します。
たとえば、やせた身体のもつ万能感や賞賛、庇護、過食(気晴らし食い)に伴う恍惚感、満足感、排出行為に伴う自己浄化行動など、甘えや対象への一体化という幻想などの隠喩は、容易に自己愛の病理を隠蔽してしまい、嗜癖や依存行動としての側面が強調されるようになるのです。
そのような摂食障害と依存の心性の違いについて、野間先生の本を読んでみましょう。
摂食障害が本来の生を生きるための営みであり、依存症一般もやはりそうであるなら、食の病は依存症の治療ストラテジーで克服できるにちがいない——そう考えるのは、じつに自然な発想である。
しかし、現実にはそううまくはいかない。
摂食障害患者に対してアルコール依存や薬物依存に対するものと同じ治療を行ったり、それらの依存症患者といっしょに集団精神療法を行ったりする試みがいくつかなされてきたが、いずれも失敗に終わっている。依存症者もたしかに、自分を一番大事に考え、自分に甘くなってしまうという意味で、自己愛に満たされている。
しかしそれは、自分を前面に出すことのない、いわば「消極的な自己愛」である。
依存自体は、現実のつらい壁を前に独り自分を慰める行為ともいえる。
自助グループは孤立を防ぎ、参加する依存症者はともに互いがここに存在している意味を確認し合い、依存そのものを無力にする。まさに集団の力が、そこにある。それに対して、食を病む者は、つねに「自分」が第一の関心事であり、そこにあるのは「積極的な自己愛」である。
主体的自己は、あくまで周囲世界の支配を志向する。
他者とともに生きようとしても、そこで他者への対抗心が惹起されて逆に孤立を深めてしまい、さらに食の苦悩が悪化する危険がある。
このように、摂食障害患者からなる集団は、つねに捩れる運命にある。
彼らにあるのは、まさに徹底した自己愛である。ナルシスが近づこうとする他者は自らを映す水面でしかなく、それへの接吻には死が約束されている。
『解離する生命』「愛のキアスム」
依存症の心性が自己慰撫であるのに対して、摂食障害の心性は自分への関心ということですよね。
つまり甘えや対象への一体化ということは、自己不信、等身大の自己の欠如を隠匿するための融合転移(わかってくれて当然)、鏡映転移(賞賛されて当然)の現れであり、これが「周囲世界の支配を指向する」ということですね。
同じ依存の構図を背景にしているとはいえ、これまで述べてきたように、食の病にみられる依存のあり方は、ほかの依存症とは質を異にする。
つまり、依存症者は一般に他者を愛し他者から愛されることを臨むが、摂食障害者の場合は、本来的にもっている深い自己愛のために、他者と繋がることではなく他者から一方的に愛されることを臨んでいる。
しかし、一方的な愛を希求することによって、当然ながら他者との断絶が生まれる。本来は「ゾーエーへの回帰」を望んでいるにもかかわらず、深い自己愛のゆえ、表面的には他者と距離をとる「ゾーエーの回避」を余儀なくされているのである。
彼らは、人格的自己を無理やり作り上げ、周囲世界を支配し、他者との生き生きとした関係を成立させているゾーエーから遠ざかりながら、それでも本当は、一方的に無償の愛を得ることを望んでいる。
それは明らかに矛盾した姿である。
そのような矛盾が、さらに彼らの食の病理、対人関係の病理を深める。
その結果待っているのは、徹底した究極の孤独でしかない。
これは、自閉的な孤高ではない。愛を求めながら自らそれを拒絶するという、自己矛盾した悲劇的で救い難い孤独である。
『解離する生命』「愛のキアスム」
「せめてやせた体型でないと取り柄がない」という思いは、他人から見て、輝いている自分でないと(自分自身も)受け入れられないという「人からどう見られるか」という自尊心・自己愛の病理ですね。精神病理学者の木村敏に倣って、「生命体(ビオス bios)」としての生命的自己の背後に「生一般(ゾーエー zoe)」の存在と仮定し、個体としてのビオスを混沌たる無形のゾーエーの個別化と考え、死の欲動を「ゾーエーへの回帰」と捉えるならば、摂食障害という自己破壊に死の欲動を見ることは不可能ではない。
現実のみならず、自己評価においても他人が自分をどうみているのかを気にし、自分が受け入れられているのかどうか、他者の顔色を見てしまう傾向にあり、他者の目(まなざし)が自分の姿を映す鏡になっているのですね。
まなざす他者は意識されながら、自らのまなざしが他者性を有しているだけで、実のところ、他者は不在であるところに自己愛の「究極の孤独」が見えてきますよね。
次回は、摂食障害と衝動性についてみていきます。
院長