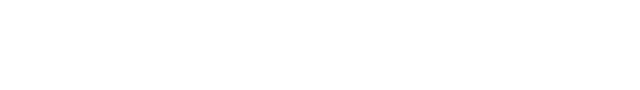夢から覚めて

今日は患者として治療を受けた経験があるということと、治療者になるということには大きな違いがあるというジレンマの中で見た「ある夢」について書いてみようと思います。
広い体育館の中を、学生服を着た弟が天井に向かって銃を放ちながらよろよろと歩いています。周りには数人の同級生らしき人物と私がいて、弟の後を追っています。
弟は汗だくで床に倒れこみ、口からは血液混じりに唾液がこぼれています。息も絶え絶えになっている弟に駆け寄った私は、彼の手を握りしめながら「逝かないで、逝かないで」と泣きながら声をかけました。けれども暫くして、私は「弟はもう助からないんだ」と直感しました。
その瞬間に、私はどうしたら弟が少しでも安らかに息を引き取ることができるのか、なんと語りかければいいのか、ということを考えていました。そして、「ここにいるよ、大丈夫だよ。」と繰り返していました。それを聞いた弟の表情が一瞬穏やかに見えたところで、私は夢から覚めたのでした。
私はすぐにベッドから起きて、泣きながら今見た夢をノートに記しました。そして、書きながらまた、胸に迫る想いを体感していました。夢の中で死にゆく弟を目の前にして、私はもうどうやっても助からないのだという現実を受け入れざるを得ませんでした。そして、自分にはどうすることもできないんだという絶望の淵に立たされた私は、ここで「逝かないで」と弟に語りかけることは私自身のエゴに過ぎないのだということを突きつけられた気がしました。
そして初めて、今目の前にいる弟は私に何と言ってほしいだろうか、この状況で私だったら何と言ってほしいだろうか、という考えに行きついたのでした。それは私にとって痛みを伴った苦しい決断でした。自分のエゴを手放して、相手の心にどれだけ寄り添うことができるのか。その覚悟を、私は夢の中で迫られたような気がしました。
その同じ週にこんな出来事がありました。ある患者さんが、「私は病気ではありません。ただ誰よりも痩せていたいだけなんです。こんなに太ってしまってもう生きている意味がありません。急には太らないって言ったのに先生の嘘つき!」と言いながら診察室で泣きじゃくりました。
私は2年前に彼女と最初に会ったときと同じような彼女の言葉を聴きながら、「今の彼女に対して私に何ができるのだろう。何もないのだろうか…。」という無力感でいっぱいになっていました。そして、その気持ちを正直に伝えることしかその時の私にはできませんでした。
夢をノートに書き留めた後、私は彼女とのやり取りを思い返していました。そして、これまでの私がいかに自分本位であったかを痛感しました。あの時の私は、彼女の声に本当に耳を傾けていただろうか。「病気ではない」「誰もわかってくれない」という彼女に対して私は正論でぶつかるだけで、彼女が診察室を一歩出た世界の中でどんなふうに生きているのかを想像してみただろうか。
医者という鎧と知識という武器を手に、私は彼女の病気の部分と必死に闘っていました。そして彼女の病気と敵対すればするほど、私の何とかしたい、という気持ちがどんどん大きくなっていったような気がするのです。けれども私の「何とかしたい」は、彼女の同意もなければ彼女の意志に添うものでもありませんでした。私の独りよがりだったのです。
思えばこれまで私は、患者さんに対して自分の思いを伝えることに一生懸命になっていました。それがいけないことではないと思いますが、治療は決して私の一人舞台ではなく患者さんとの共同作業なんですよね。そして医学的に正しいことと、患者さんにとっての真実は必ずしもイコールではないということにも改めて気づかされたように思います。
むしろ、自分の中の「何とかしたい」を自覚し横に置いたうえで、患者さん自身の文脈に添ったストーリーを一緒に紡ぎながら患者さんのニーズや利益を探っていくことが大事なのではないでしょうか。それでは医師は患者さんが明らかに医学的に誤った選択をしようとしていてもそれを黙って見過ごすのか、とおっしゃる方もいるかもしれません。そんな時、私はこの言葉を思い出します。
「信は医の心 情は医の涙 学は医の力 理は医の砦」
織田敏次 PHP誌 1993年3月号より
これは私が高校生の頃偶然目にした言葉なのですが、とても心に響いたので高校の書道の先生に色紙にしたためていただき、今でも大切に持っているものです。今回の一連の経験は、患者さんのニーズやメリットは何かと考えるとき自分のエゴを手放すこと、そして「理」の一線を守りつつ「信」、「情」、「学」それぞれの要素を併せもった視点が大切であることを教えてくれたような気がします。