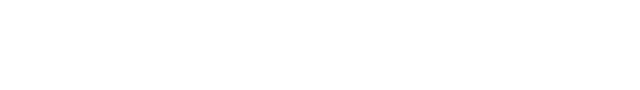刹那の反転6〜共感のまなざし
『刹那の反転5〜意味づけとエクスポージャー』で、「受動性から能動性への反転不全」という「受動体験」であるトラウマティックな体験は、「意味づけをする」という能動的な態度(エクスポージャー)により外傷の要素を無効にすること(レジリアンスを回復すること)が可能で、その土台になるのが「共感」ということをみてきました。
“共感”とは何なのか?そして、なぜ“共感”は絶大な治療効果をもっているのか?この問いに答えることは、簡単なようでじつはたいへん難しい。
宇田亮一・著『吉本隆明『心的現象論』の読み方』(文芸社)
ということを今回はみていきます。
野間俊一先生はこうおっしゃっています。
ここでの患者と治療者の関係とはどのようなものだろうか。
患者が治療者になんらかの感情を抱いたとしても、それは良い感情ばかりとは限らない。
治療者に対する不満であったり、失望であったり、恨みであったりするかもしれない。
しかし、そのような感情が治療場面において表面化するということは、治療者が、そして治療空間が、そのような感情の表出を許容してくれるだろうという信頼感が前提として存在する。
それは、「感情の内容を理解してもらえるという信頼」なのではなく、「感情をもつことそのものが受用されるという信頼」である。
野間俊一・著『身体の時間』(筑摩選書)
つまり、共感の基盤は、「感情の内容を理解してもらえるという信頼」なのではなく、
「感情をもつことそのものが受用されるという信頼」というのです。
ここでふたたび他者から「まなざされる」ことで“投影”と“取り入れ”によって動態化していく、というテーマが浮上してきたようです。
つまり、「“共感”とは何か」ではなく、「“共感”の初源とは何か」を問うのである。それは乳幼児期の“母子関係”にまでさかのぼることを意味する。
宇田亮一・著『吉本隆明『心的現象論』の読み方』(文芸社)
少し長くなりますが、宇田亮一さんが描写するカウンセリングの現場を読んでみましょう。
カウンセリングの現場で、クライエントは自分の心の中にある「なにかモヤモヤしたもの」を語っているうちにセラピストがそれに言葉を返していく。
セラピストが返す言葉は、厳密に言えばセラピスト自身のものにすぎないのだが、まるでクライエントのものであるかのようにクライエントに返っていくのである。そして、こうした関係の中でクライエントに気づきが起こるのである。このようなやり取りによって、クライエントの硬直した、あるいはパターン化した“心”に再び柔軟性や弾力性が息を吹き返してくるのである。
赤ちゃんの“心”が動態化したようにクライエントの“心”が動態化するのである。
セラピストが母親と同質の“まなざし”をクライエントに向ける時、クライエントに治療的な変化が生じるのである。
これが“共感”の正体である。いいかえれば、セラピストがクライエントに“共感”の“まなざし”を投げかけた時、クライエントに治療的な変化が生じるのは、クライエントが、かつて母親との関係において“心を能動化させた”ことの学習効果だといえる。
クライエントとセラピストとの関係において乳児期の母子関係が再現、あるいは反復されるのだ、といってよいだろう。
クライエントはセラピストの“まなざし”に母親の“まなざし”を重ねているのだ。これこそが“共感”の絶大な治療効果にほかならない。
宇田亮一・著『吉本隆明『心的現象論』の読み方』(文芸社)
息が詰まるような圧倒的な描写ですよね。
『愛着(アタッチメント)と治療関係』や『安全基地としての治療者』『愛着障害の癒しに必要な治療者のあり方』で触れたようなセラピストの姿が浮かび上がりますよね。
つまり臨床という場は、「まなざすこと」を通じてクライエントの意識を呼び覚まし、原初的な身体反応の中に埋没した愛着のプロセスをなぞることで、因果という経験的な時間を紡ぐこと(「ものがたる」こと)により、受動から能動への反転により外傷体験の無効化を可能にしていると考えられますよね。
院長