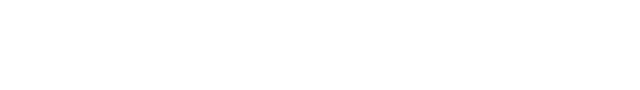クセになった過食と対人恐怖的回避型アタッチメント
このところ『愛着障害としてのアディクション』からの引用が増えていますので、改めて「アディクション(嗜癖)」と「依存」の違いを整理しておきましょう。
『摂食障害の謎を解き明かす素敵な物語』には、「この章では依存という言葉を何度も使っていますが、摂食障害はアルコール依存や麻薬依存のような物質依存ではなく、行動依存だということを覚えておいてください。つまり、乱れた食行動に苦しむ女性は、食べるという行動に依存しているのであって、食べ物に依存しているわけではないのです」と、「行動依存」という言葉を使ってありますよね。
「摂食障害における嗜癖性の臨床的意義」(精神科治療学 33(11): 1321-1325, 2018)という論文では、「離脱症状の存在や体制の獲得といった固有の特徴をもった「依存」(あるいは「依存症候群」)という科学的概念に対して、「嗜癖(アディクション)」は「報酬刺激に対する強迫的関与」を意味する幅の広い概念である。ここでは、「報酬刺激を求める強迫性」を「嗜癖性」と呼ぶことにする」と説明されています。
上記の論文から引用しますね。
ここであらためて、摂食障害の食行動の嗜癖的な側面を整理しておきたい。まず、「食物嗜癖」という概念が過度に広まり、過食を物質嗜癖と同様に扱うことは避けなければならない。
(中略)
物質への嗜癖も存在するのだろうけれども、それよりはむしろ、摂食行動という行動に嗜癖が生じた「行動嗜癖」と理解し、食べる内容だけではなく食べるという行為そのものに対する嗜癖(「摂食嗜癖(eating addiction)」)があると考えるべきだろう。
このように嗜癖を広く「報酬刺激を求める強迫性」と理解したうえで、摂食障害の病的行動に照らしてみよう。すると、過食や嘔吐、下剤乱用はもちろん、過活動など、多くの症状が強迫性をもっていることがわかる。
さらにこれらの症状は、苦痛を伴うことも事実ではあるが、例えば過食なら普段制限している甘いものや高カロリーの食物を摂取できるという快感を伴っているのは事実であり、嘔吐や下剤乱用、過活動といった代償行動は体重を増やさずにすむという安心感につながっている。代償行為の場合は、苦痛を伴いながらもそれをやりきった時の解放感は、安心感と相まって大きな快感につながるはずである。
野間「摂食障害における嗜癖性の臨床的意義」精神科治療学 33(11): 1321-1325, 2018
「摂食嗜癖(イーティング・アディクション)」、つまり『素敵な物語』で言う「行動依存」は、厳密には「摂食行動嗜癖」であり、「過食という報酬刺激を求める強迫性」だということですね。
過食症の治療目的で受診した患者さんに強迫性障害の検査をやってもらうと、ほとんどの患者さんにいくつもの強迫観念・強迫行為が認められます。
しかも、これらの強迫観念・強迫行為は自我違和感に乏しい(苦痛を伴わない)のが特徴で、多くの過食症の場合、強迫性障害の合併・併存は見逃されています。
このような自我親和的な強迫性である「摂食行動嗜癖」によって、「過食がクセになった」「食べ吐きが習慣化した」と感じられるのです。
報酬刺激を「過食」という形で強迫的に求めざるを得ないのは、心の中でうごめく情動を内的に処理することができずに外的に対処しようとする、自己慰撫あるいは自己治癒の試みと理解されるようになってきました。
対人的回避や感情の過剰な抑制を特徴とする「感情抑制型」の人が、どのようにして過食(むちゃ食い)や過食嘔吐という「報酬刺激を求める強迫性」にとらわれてしまうのか、『過食症:食べても食べても食べたくて』の第2章「怖がらずに何でも食べる」からリンジーさんの体験を見てみましょう。
私が子ども時代について覚えている全般的な印象といえば、家族の所有する十四エーカー(約56,700平方メートル)という広い敷地をさまよっているときも、夕食の食卓に座っているときも、ひとりぼっちだったということです。
何か悪いことをしてしまったのだと、しばしば怯えていたことを思い出します。
問題を起こす気などなく、それどころか私は、常に完璧な少女でいようとしていました。それにもかかわらず、私は四六時中しくじってばかりという感覚にさいなまれていました。
ホール&コーン『過食症:食べても食べても食べたくて』星和書店
幼少期はのリンジーさんをクロニンジャーの七因子モデルで考えてみると、「新奇性追求」と「報酬依存」が低く、「損害回避」と「固執」が高い「回避型」の気質を持っていたようです。
りんじーさんは、漠然とした不安を抱えて「いい子でいなければならない」と考えるような、自尊心が低い強迫的な子どもだったようです。
自分がいかに怯えているのかさえわからず、未来への不安を伝える方法もわからないまま、私は泣く泣く家を出ました。
それから何カ月も、私はささいなことがきっかけで泣いていました。親とは感情的な問題を分かち合った経験が全くなく、友人に相談したこともありませんでした。
本当のところ、自分を悩ませているものが何であるのかさえわかっていませんでした。分かっていることといえば、自分がどうしようもなくみじめであり、ひどく寂しく感じていることだけでした。
ホール&コーン『過食症:食べても食べても食べたくて』星和書店
14歳で全寮制の学校に入学した思春期・青年期のリンジーさんは、生きづらさを抱えて、わけのわからない不安に押しつぶされそうになりながらも、助けの必要性を遮断して誰かに助けを求めることを避けていますよね。
過食や過食嘔吐などの摂食障害行動は、外的なストレッサー(ストレス要因)によって引き起こされたストレス反応によって引き起こされるという考え方は、リンジーさんの体験にはマッチしませんよね。
アタッチメントの文脈で考えると、リンジーさんは、養育者からの応答が少なかったために社会的関わりを満足させることを学ぶ機会が乏しく、他者の存在にアタッチメント行動を起こさない傾向があったようです。自分自身で無力感を感じ、感情と行動レベルの低さ(すなわち、保身や引きこもり状態)が特異的な「対人恐怖的回避型アタッチメント(遠ざかり境界性自己障害)」のようです。(『回避型アタッチメントと摂食障害』参照)
また、全寮制の学校で暮らすリンジーさんは、現在の養育者(親)との関係が摂食障害行動の維持因子になっているとは考えにくいですよね。(『家族関係とひとり暮らしと乱れた食行動』参照)
リンジーさんの摂食障害行動の維持因子を考えてみると、内部状態の気づきも乏しく、身体的あるいは情緒的な不快さと本人が感じている心理的状態との間にある分離、つまり、「内的な心理状態(どうしようもなくみじめ)」と「身体的状態(ささいなことがきっかけで泣く)」との間の不一致や一貫性のなさが関係しているようです。しかも、その「一貫性のなさ(同一性の拡散)」にリンジーさん本人はまったく気づいてなかったようです。
身体感覚は生理的状態の変化によって引き起こされます。この生理的変化は、「自分がいまどんな状態にあるのか」という情報であり、「何を必要としているのか」を知ることと関連しています。
リンジーさんは、自分が怯えていることもわからず、身体的状態(ささいなことがきっかけで泣く)が指し示す文脈も読み取れませんでした。
スティーブン・ポージェスの「ポリヴェーガル理論(多重迷走神経理論)」によると、リンジーさんのような状態は「背側迷走神経の緊張亢進状態(シャットダウン:不動状態)」と呼ばれます。
このようなタイプの人には「耐性領域を広げていく」、つまり身体感覚をモニターしながら対人関係の相互作用的調整を強化していくような、ゆっくりと進める治療が必要になります。
三田こころの健康クリニックで行っている対人関係療法による過食症の治療でも、自分の身体を感じることを通して気持ちや考えを知る練習を始める場合もあるのは、このような理論背景があるからなのですよ。(Tamikoさんの「【治療記録4】体の声を聞く方法」を参照してみてくださいね)
院長