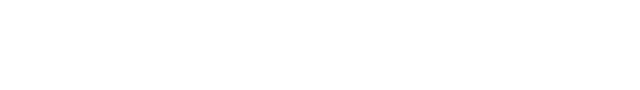摂食障害から回復するためにはどのような治療者を選べばいいのか
他者に対して情緒的に何ら求めることがなく、有効に機能し、自分自身の欲求を自覚していないかのように見える「遠ざかり境界性自己障害」は「対人恐怖的回避型愛着スタイル」とオーバーラップしているように見えますよね。
対人関係と距離を取ることで安心を得ている〔対人恐怖的回避型愛着スタイル〕から〔獲得安定型〕に移行する際に、覆い隠されていた愛着欲求と不満・怒りなどの葛藤が表面化し、一時的に〔おそれ型(未解決−無秩序型)〕から〔アンビヴァレント型(とらわれ型)〕のような状態が出現することがよくあることが知られています。
〔アンビヴァレント型(とらわれ型)〕のような状態とは、感情を隔離・回避していた心の蓋が開き、見捨てられ不安(依存欲求)と試し行動(怒り)が同時に高まった状態です。
「そのような回避的な生き方を続けていては、摂食障害が治ることはけっしてない」という事実を告げます。
摂食障害の患者さんは、そのような「本当のこと」を言われる事に、強く反発します。そんなことを言う相手が、いかにも無理解で、無神経で、無慈悲で、人を傷つける人でなしであるという反応をします。
「それ(ここでは、自己誘発嘔吐のこと)をやっていては、病気は治らない。だから、やめる必要がある」と言ってくれる治療者と、「症状だから言っても仕方ない」と容認する治療者では、治す力が全然違ってくるのです。
瀧井「摂食障害の精神病理に真摯に向き合うことの重要性」 in日本摂食障害学会ニュースレター No.22
『摂食障害から回復するための8つの秘訣』の〔秘訣6 自分の行動を変えるということ〕には、「実際の治療では、むしろ嘔吐をやめる介入から始めます。(中略)まずやめるべき行動は、嘔吐ということになります。どんな理由があろうと、嘔吐することをやめる努力をしてみましょう」と書いてありますよね。
しかし患者さんにとっては、いままで見ないようにしてきた、なかったことにしてきた、自分の中の恐怖(摂食障害の病理)と向き合わざるをえなくなるので、このプロセスはとても苦痛に感じられます。この時に治療者との間で〔アンビヴァレント型(とらわれ型)〕のような関係が再演されることもあるのです。
アタッチメントの変容プロセスでも、摂食障害の治療過程でも、治療者のスタンスが非常に重要になってきますよね。
問題は、ゴムボートと違って援助者はアディクト本人と同じ人間であり、同じように感情を持っているという点にある。
人は誰でも、誰かに信頼してもらうと嬉しい。信頼してもらえるだけの価値がある存在であると、自分自身について実感することができるからである。
乳児期の子どもが親に与えてくれる最大のプレゼントは、まさにこの無条件の自己肯定感であろう。
小林『人を信じられない病 信頼障害としてのアディクション』日本評論社
患者さんに信頼してもらえることで治療者が自己肯定感を得ている状態を、「メサイア・コンプレックス」「救世主願望」と呼んだりします。
「救世主願望」を抱えた治療者は、患者さんあるいはクライエントさんを自らの自己肯定感を充足させてくれる対象として利用しているということなのです。
自己肯定感は甘い蜜である。
そしてもし、アディクションの援助者自身がもともと何らかの理由で甘い蜜に飢えていたとしたら、アディクトを援助することによって比較的容易に援助者自身の飢餓感を満足させることができてしまう。
表面上はアディクトのために行動しているように見えるので、目的がいつの間にかすり替わってしまっていても、この罠に援助者本人でさえなかなか気づくことができない。
小林『人を信じられない病 信頼障害としてのアディクション』日本評論社
治療者が自身の人生についてどのように内省しているかが、クライエントの変化に影響を与えると考えられています。
正式に精神療法や心理療法のトレーニングを受けると、教育分析(訓練分析)の過程で自らの抑圧や回避などの心のクセや、メサイア・コンプレックスをスーパーヴァイザーから指摘されることで治療者として一人前に成長していきます。
しかし正式なトレーニングを受けていらっしゃらない有名な精神科医や、摂食障害を克服した自称カウンセラーさんの中には、患者さんクライエントから信頼を寄せられることで、自らの自己肯定感や自尊心を満足させていらっしゃる方も時々みかけますよね。
これらの人たちに共通するのが、自分を振り返ることができないことと、自分は患者さんクライエントさんのために尽くしている、必要な人に必要な情報を届けている、という自己陶酔(自己愛の病理)です。
このように心の奥にナルシシズムの病理(自己愛の傷つき)を抱えた援助者は、一見するとアディクトの心理的孤立と共鳴してすぐに信頼感を勝ち取ることができてしまうのだが、結果的には、アディクトへの支援という目的が、みずからの自己愛を満たすための手段と化してしまう。
小林『人を信じられない病 信頼障害としてのアディクション』日本評論社
ナルシシズムの病理を抱えた治療者は、重要な他者との数多くの決定的な失敗体験を重ねてきたがゆえに「心理的孤立と無力感」を食べる行為で紛らわしてきた摂食障害の患者さんたちと共鳴しやすく、甘く耳あたりのいい言葉で容易に信頼感を勝ち取ることができるようなのです。
精神病理をより深く理解できるようになることが、摂食障害治療者の成長だとも言えます。
甘く考えて、病理には触れず、耳触りのよいことばかり述べている医療者もすくなくありません。
はじめは患者さんや家族から「良い先生」とおだてられ、でもいざとなったら何もできず…(この行間を察してください)、それでも自分のやり方を変えられない悲しい専門家(?)も少なくないのです。
瀧井「摂食障害の精神病理に真摯に向き合うことの重要性」 in日本摂食障害学会ニュースレター No.22
朴訥とした父親(その治療者によって発達障害と誤診されている)を娘の摂食障害の治療に影響があるからと強制別居させたり、母親が働いていたことが摂食障害の発症につながったとして、その埋め合わせに杖歩行の70歳近い母親に、1日に何回も過食のための食材を買い出しを強要する「悲しい専門家(?)」たちもいるのが現状です。
専門家を自称するこのような治療者(?)たちは、治療同盟関係ではなく患者さんの代弁者であると自認し、治療者自身の問題を患者さんのご両親に向けているように思えます。
治療技法のみに流されては有効な治療にはならない。依存症者は健康な人との関わりにおいてこそ回復する。
(中略)
「どの治療法」を選択するかより、「誰が」治療を行うか、が治療効果を左右する。「誰が」とは、「共感性の高い治療者」「偏見や陰性感情から解放された治療者」を指す。
成瀬「依存症のクライエントと向き合う際の心得」in 『やさしいみんなのアディクション』金剛出版
ランブルスコ(Lambruschi)らによると、ベテラン心理療法家たちの半分以上が、自分の問題に無自覚なまま患者の世話を通して自らの未解決の問題を修復しようとしていると考えられる、と述べています。
治療者は、自分自身と患者との適合性も評価すべきである。患者同様、治療者自身も独自の愛着とコミュニケーションのスタイルを持つため、「己を知れ」という格言を強調してしすぎることはない。
例えば、過度に指示的な治療者は、回避型の患者とは難しいかもしれない。治療を終結させるのが困難な治療者が、依存的な患者との問題に遭遇する可能性もある。
スチュアート「短期対人関係療法」 in デワン・他『短期精神療法の理論と実際』星和書店
『摂食障害から回復するための治療関係』で書いたように、「モデル(目標と感じることができる人)」「メンター(経験に基づき助言してくれる人)」「サポーター(アタッチメント対象としての心理的な支え手)」として機能する治療者を選ぶ必要があるということですよね。
院長