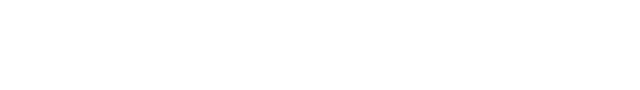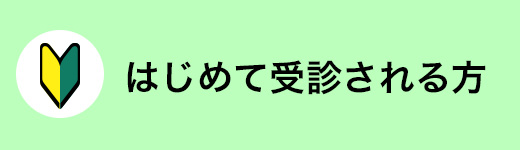統合失調症
統合失調症とは
統合失調症とは、考えがまとまりにくく現実との区別が難しくなる精神的な病気です。以前は「精神分裂病」と呼ばれていましたが、2002年に「統合失調症」という名前に変わりました。
患者数は人口の約1%とされており、決して珍しくない病気です。10〜30代の若い年代で発症する方が多く、学校や仕事など社会生活や日常生活を送るのに支障が出ることが多いのが特徴です。
幻覚や妄想などの「陽性症状」、意欲の低下や感情を表に出さなくなるなどの「陰性症状」、集中力や記憶力、問題を解決する力などの低下が見られる「認知機能障害」という症状があります。
幻覚や妄想が代表的な症状ですが、初期の段階では不安や緊張のみが目立つこともあり、統合失調症と診断されるまでに時間を要する場合もあります。
統合失調症は以下の3つのタイプに分類されます。
| 妄想型 | 妄想や幻覚が主な症状 |
|---|---|
| 解体型 | 考えがうまくまとまらない、意欲障害が主な症状 |
| 緊張型 | 興奮や昏迷が主な症状 |
統合失調症は適切な治療により症状のコントロールが可能です。気になる症状がある方は早めに専門医へ相談することをおすすめします。
統合失調症の原因
統合失調症の原因は、今のところはっきりわかっていません。脳のある物質(神経伝達物質)のバランスが崩れて、乱れることが関係しているとされています。
また遺伝や妊娠出産時の問題、社会的な環境によるものなど、さまざまな原因が重なり発症すると考えられています。
家庭環境や子どもの育て方が原因で発症するわけではありません。また両親が統合失調症の場合でも、必ず子どもに遺伝するわけではありません。
統合失調症の症状
統合失調症の症状は、大きく分けると以下の3つにわけられます。
- 陽性症状:通常はない思考や行動が現れること
- 陰性症状:通常あるはずの機能や行動が減少または失われること
- 認知機能障害:日常生活に支障をきたすこと
それぞれの例をくわしくみていきましょう。
陽性症状
「幻覚」や「妄想」が主な症状です。また考えが止まらない、まとまりがないなどの症状もみられます。その結果、周囲に対して不安や恐怖などの不信感を抱き、孤独を感じやすくなります。
- 実際にはないものが見えたり、聞こえたりする
- 自分が誰かに狙われていると確信している
- 自分が自分でないように思う
- 考えがまとまらない
- 突然泣いたり、怒ったり感情の波が激しい
- 自分は病気でないと思っている(言う)
陰性症状
意欲の低下や周囲に無関心になる、集中力が低下するなどが主な症状です。周囲とのコミュニケーションが取れなくなり、孤立しやすくなります。また陰性症状は、周囲から「なまけている」「社会性がない」「常識不足」などと誤解を受けやすく、人間関係に支障をきたす可能性があります。
- 嬉しい気持ちや悲しい気持ちが感じにくくなる
- 会話での抽象的な表現が理解できなくなる
- さまざまなことに対し、意欲がでない
- 社会生活から遠ざかり、引きこもりがちになる
- 頑張りたいけど頑張れない
認知機能障害
理解力や記憶力の低下、問題解決能力の低下などが主な症状です。また会話しているときでも、ほかの音やものに気を取られ落ち着きがなくなります。
- 集中力や注意力が続かない
- 空気を読めない
- 食事を作る時や洗濯をする時に順序立てられない
- 同時に二つのことができない
- 物事を覚えるのに時間がかかる
- 細部までのこだわりは強いが、全体の把握ができない
では、症状がどのように経過していくのか次の章でくわしくみていきましょう。
統合失調症の経過
統合失調症は、主に以下の経過をたどります。
| 前兆期 |
|
|---|---|
| 急性期 |
|
| 休息期(消耗期) |
|
| 回復期 |
|
出典元:奈良市役所
それぞれの時期や期間には個人差があります。また統合失調症は、一旦症状が落ち着いても再発することが多いのが特徴です。そのため、再発を予防することが症状をコントロールするうえで重要です。
統合失調症の診断
統合失調症も、ほかの精神疾患と同じようにアメリカ精神医学会が定めるDSM-5やWHO(世界保健機関)が定めるICD-11の診断基準をもとに、問診による症状の確認をします。
問診では下記の項目をもとに、生活状況や既往歴なども確認します。
- どのような症状が出ているか
- 症状はいつから始まったのか
- 症状はどのように経過しているか
- 日常生活にどのくらい影響が出ているか
患者さまの症状や経過のほかに服薬状況、生活歴や家族歴などを総合的にみて診断します。また、別の病気が隠れてないか確認するため、血液検査、CTやMRIなどの画像検査を用いることがあります。
統合失調症の治療法
統合失調症の治療では、症状を落ち着かせる「薬物療法」と、再発予防を目的とした「心理療法・生活訓練」を組み合わせます。それぞれくわしくみていきましょう。
薬物療法
統合失調症の治療では、薬剤を使って症状を安定させることが大切です。
薬物療法では、「抗精神病薬」が治療の中心になります。抗精神病薬の目的は、過剰な情報伝達(ドパミン)を抑えることです。
抗精神病薬のほかにも症状に合わせ以下のような薬剤が併用されます。
| 睡眠薬 | 不眠の改善のため |
|---|---|
| 抗不安薬 | 気分を落ちつかせる、うつ症状の改善、不安症状の改善のためなど |
それぞれの薬剤は同じ目的であっても多くの種類があります。そのため主治医は患者さまの症状に合わせて、使用する薬剤を決めます。
統合失調症の薬剤療法では、「中断」がひとつの課題です。症状が一時的に落ち着くと、薬を自己中断するケースがよくあります。
症状が落ち着いているからといって、薬物療法を中止すると1年以内に約80%、2年以内に98%の方が再発すると言われています。
そのため、症状が落ち着いた時でも、自分の判断で薬を中断しないことが再発を防ぐために重要です。
心理療法・生活訓練
自分の病気への理解や、社会生活を送るための訓練を行います。「自信」や「やる気」などを取り戻し、安定した生活を送るために薬剤療法とあわせて行います。個人の症状や生活によってさまざまな方法があります。
ここで例をみてみましょう。
| 心理教育 | 病気とうまく付き合う方法を学ぶ |
|---|---|
| 生活技能訓練(SST) | ロールプレイを通し対人関係について学ぶ |
| 作業療法 | 園芸や料理などを通して、生活機能の回復を目指す |
| 就労支援 | 援助つき雇用プログラム、病気に理解のある職場を探し、生活の中でリハビリが行えるようにする |
心理療法・生活訓練を通して、社会復帰や自立に向けた体力や集中力の回復・ストレスへの対処方法などを学びます。
また、治療を進める時に家族や周囲の方のサポートもとても重要です。家族や周囲の方などの理解やサポートが、統合失調症の治療継続や社会復帰において回復を促す重要な後押しとなります。必要な支援の具体例は以下の通りです。
- 統合失調症の正しい知識を得ること
- 適切な治療を受けられるよう、通院や服薬管理などサポート
- 再発の兆候に注意
周囲の方々の協力や理解が患者さまの日常生活を支える上での重要な役割です。
統合失調症でお困りの方へ
統合失調症は、適切な治療を受けることで症状をコントロールすることが可能な病気です。
患者さま一人ひとりの具体的な症状や生活背景などを考えた治療計画に沿って、治療を継続することが、症状をコントロールするうえで大切です。
病気である認識が本人ができなくなっている場合は病院へご相談ください。本人が困っていて治療を希望されている場合は、当院までご相談ください。
執筆者紹介
大澤 亮太
医療法人社団こころみ理事長
精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了